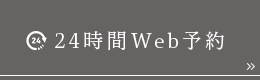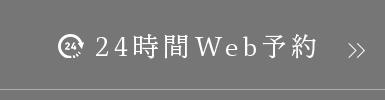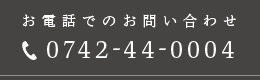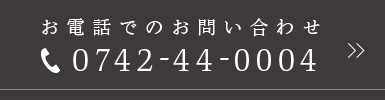内科

必要に応じて、血液検査、血圧検査、レントゲン検査、超音波検査などを行い、正確な診断に努めております。
このような症状・疾患でお悩みではないですか?
- 風邪
- 発熱
- 咳、喉の痛み
- 頭痛
- 吐き気、嘔吐
- めまい
- 慢性疲労
- 倦怠感
- 脂質異常症
- 高血圧
- 糖尿病
- 肺炎
- 冷え性
- 偏頭痛 など
冷え性
手足が冷える、体温が低い、すぐにお腹を下す、下半身が冷えるが上半身がほてるといったときには、冷え性が疑われます。冷え性でお悩みの方は詳しくはこちらをご覧ください。
偏頭痛(片頭痛)
ズキンズキンと脈打つ痛みが特徴で、一般的には頭の片側に起こります。しかし、両側性で締め付け感のある頭痛も、偏頭痛と診断される場合があります。吐き気や嘔吐を伴うことが多く、痛みで寝込んでしまったり、体を動かすと悪化したりします。
偏頭痛発作は、疲労・ストレス、睡眠トラブル、天候の変化・温度差、月経などが因子となります。誘発因子には個人差があるため、ご自身の発作が起こりやすい状況を把握しておきましょう。
その他、ちょっとした体調不良なども、お気軽にご相談ください。
※発熱がある方は、お電話にて一度ご相談下さい。
循環器疾患
このような症状・疾患でお悩みではないですか?
- 動悸、息切れ
- 胸が苦しい、痛い
- 冷や汗が止まらない
- 頻脈、徐脈
- 立ちくらみ、ふらつき
- 高血圧
- 狭心症
- 心筋梗塞
- 不整脈
- 心臓弁膜症
- 心不全
- むくみ
など
当院では生活習慣病の診療を行っています

生活習慣病は、症状が乏しい一方で、進行すると心筋梗塞や脳卒中のリスクを高める病気です。
特に健康診断で数値の異常を指摘された方は、年齢に関係なくお早目にご相談ください。
生活習慣の改善、薬物療法などによる治療を行います。
また、生活習慣病の予防に取り組みたいという方もお気軽にご相談下さい。
メタボリックシンドローム
男性で85センチ以上、女性で90センチ以上の腹囲がある状態、また加えて高血圧、脂質異常症、糖尿病のうち2つ以上の合併がある状態を指します。
症状・リスク
メタボリックシンドロームは、自覚症状が出ることが少ないことから、放置する患者さんが多くいらっしゃいます。
しかし、2型糖尿病や非アルコール性脂肪肝、高尿酸血症、腎臓病、睡眠時無呼吸症候群を引き起こす可能性があります。
また、動脈硬化が進みやすい状態ですので、心筋梗塞や脳卒中といった命にかかわる病気のリスクも高くなります。
原因
メタボリックシンドロームになる原因として、出生時の環境や親の生活環境かかわってきますが、最も考えられるのは食事・運動などの生活習慣です。
1回あたりの食事時間が30分以上で満腹になるまで食べる、間食が多くお菓子などの嗜好品を好んで食べる、移動手段に車を使い運動習慣がない、という方は生活習慣の改善が必要となります。
治療法
メタボリックシンドロームの原因となる「内臓脂肪」を減らす必要があります。そのためには、バランスの良い食事、適度な運動を意識し、無理のないダイエットを行いましょう。
5~10%の減量でも、高血圧・脂質異常・高血糖に対して十分効果が得られます。
当院の診療では、食事指導をメインに生活習慣の改善を図ります。
健康診断

検査結果に応じた適切なアドバイス、精密検査・治療のご案内を行いますので、安心してご相談ください。
特定健診は、40歳以上の、奈良市国民健康保険に加入している方が対象です(無料)。
メタボリックシンドロームに着目し、生活習慣病の発症・重症化を予防することを目的にした健診です。
予防接種

当院では、インフルエンザ、A型肝炎、B型肝炎、麻疹・風疹などに対する予防接種を行っております。